
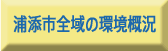
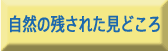
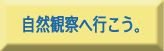
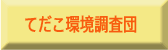
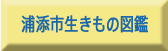
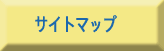
陸域動物調査
陸域動物:カタツムリについて
1. 調査結果
調査の結果、4目12科16種のカタツムリの仲間が確認されました。調査団が調査した結果を基にまとめた調査結果を下記の表に示します。
|
目名 |
科名 |
和名 |
環境区分 |
|
|
草地 |
森林 |
|||
|
原始腹足目 |
ゴマオカタニシ科 |
|
○ |
|
|
中腹足目 |
ヤマキサゴ科 |
オキナワヤマキサゴ |
|
○ |
|
ヤマタニシ科 |
|
○ |
||
|
○ |
○ |
|||
|
基眼目 |
ケシガイ科 |
ケシガイ類(ナガケシガイ) |
|
○ |
|
柄眼目 |
オカモノアラガイ科 |
オカモノアラガイ類(オキナワヒメオカモノアラガイと思われる) |
○ |
|
|
キバサナギガイ科 |
サナギガイ類 |
○ |
|
|
|
アフリカマイマイ科 |
○ |
△ |
||
|
オカクチキレガイ科 |
オカチョウジガイ類(未同定;近似種が3種ほど知られている) |
○ |
△ |
|
|
カサマイマイ科 |
|
○ |
||
|
ベッコウマイマイ科 |
ナハキビ |
|
○ |
|
|
○ |
|
|||
|
ナンバンマイマイ科 |
|
△ |
||
|
|
○ |
|||
|
オナジマイマイ科 |
|
○ |
||
|
オナジマイマイ類※ |
○ |
△ |
||
|
○ |
○ |
|||
|
4目 |
12科 |
16種 |
8種 |
14種 |
凡例 ○:生貝の確認あり、△:死貝のみの確認
※印は、種が重複している可能性があるため、種数に計上しない。
また、班ごと及び環境区分別の結果を下記の表に示します。
【A班】草地環境で確認された陸産貝類と個体数
|
和名 |
個体数 |
||
|
生貝 |
死貝 |
合計 |
|
|
オキナワヤマタニシ |
0 |
8 |
8 |
|
オカモノアラガイ類 |
28 |
6 |
34 |
|
サナギガイ類 |
1 |
1 |
2 |
|
アフリカマイマイ |
3 |
1 |
4 |
|
オカチョウジガイ類 |
7 |
24 |
31 |
|
アジアベッコウ |
1 |
0 |
1 |
|
オナジマイマイ類 |
5 |
1 |
6 |
|
オキナワウスカワマイマイ |
100 |
41 |
141 |
|
合計 |
7種 |
7種 |
8種 |
【A班】森林環境で確認された陸産貝類と個体数
|
和名 |
個体数 |
||
|
生貝 |
死貝 |
合計 |
|
|
フクダゴマオカタニシ |
2 |
0 |
2 |
|
オキナワヤマタニシ |
31 |
184 |
215 |
|
アオミオカタニシ |
2 |
5 |
7 |
|
アフリカマイマイ |
0 |
4 |
4 |
|
オカチョウジガイ類 |
0 |
1 |
1 |
|
オオカサマイマイ |
1 |
3 |
4 |
|
ナハキビ |
5 |
2 |
7 |
|
シュリマイマイ |
2 |
16 |
18 |
|
シラユキヤマタカマイマイ |
0 |
1 |
1 |
|
オナジマイマイ類 |
0 |
6 |
6 |
|
オキナワウスカワマイマイ |
15 |
8 |
23 |
|
合計 |
7種 |
10種 |
11種 |
【B班】草地環境で確認された陸産貝類と個体数
|
和名 |
個体数 |
||
|
生貝 |
死貝 |
合計 |
|
|
オキナワヤマタニシ |
2 |
176 |
178 |
|
サナギガイ類 |
1 |
0 |
1 |
|
アフリカマイマイ |
16 |
6 |
22 |
|
オカチョウジガイ類 |
0 |
3 |
3 |
|
オキナワウスカワマイマイ |
205 |
119 |
324 |
|
合計 |
4種 |
4種 |
5種 |
【B班】森林環境で確認された陸産貝類と個体数
|
和名 |
個体数 |
||
|
生貝 |
死貝 |
合計 |
|
|
オキナワヤマキサゴ |
1 |
0 |
1 |
|
オキナワヤマタニシ |
36 |
366 |
402 |
|
アオミオカタニシ |
9 |
6 |
15 |
|
ケシガイ類(ナガケシガイ) |
3 |
0 |
3 |
|
アフリカマイマイ |
0 |
2 |
2 |
|
オオカサマイマイ |
0 |
1 |
1 |
|
ナハキビ |
2 |
0 |
2 |
|
シュリマイマイ |
5 |
20 |
25 |
|
オナジマイマイ類 |
1 |
0 |
1 |
|
オキナワウスカワマイマイ |
9 |
64 |
73 |
|
合計 |
8種 |
6種 |
10種 |
環境別に陸産貝類の生息種の多様性の違いを比較するために、シンプソンの多様度指数(D)を用いて比較を行いました。算定した結果を下記の表に示します。
班ごとの多様度指数の比較
|
|
草地環境 |
森林環境 |
||||
|
生貝 |
死貝 |
合計 |
生貝 |
死貝 |
合計 |
|
|
A班(干支橋) |
0.4830 |
0.6490 |
0.5707 |
0.6361 |
0.3522 |
0.4303 |
|
B班(当山橋) |
0.1572 |
0.5111 |
0.5080 |
0.6561 |
0.6574 |
0.6088 |
生貝を比較すると、A班、B班ともに草地環境の多様度指数が低く、森林環境の多様度指数が高い結果となりました。一方、死貝を比較すると、A班は草地環境の多様度指数が高く、B班は逆に森林環境の多様度指数が高い結果となり、班によって違う傾向を示しました。
これは、死貝の殻が残存する期間に種による違いがあるため、殻が丈夫な種が多数生息していた場所では、そのような特定の種が多く確認され計数されます。その結果、偏った種が多く計上され、そのことが、多様度指数がその環境の多様性を正しく反映しない結果に繋がる要因となるためであると推測されます。
|
|
|
|
踏査の様子 |
確認されたカタツムリの分類 |
2. 環境調査
2-1 評価
【A班】
調査の結果、浦添大公園内におけるカタツムリの出現種数は16種でした。北部地域のカタツムリ類と比較した結果、浦添大公園は種数が少ないと評価しました。
【B班】
調査の結果、浦添大公園内におけるカタツムリの出現種数は、12科16種類でした。辺戸岳35種、森川(宜野湾市)14種、南風原22種と比較した結果、県内他地域(南部、北部)と比較して、やや少ない結果となりました。以上のことから、環境の多様性が乏しいと評価しました。
2-2 現状
団員が観察した浦添大公園のカタツムリの現状として、以下のような意見が挙げられていました。
|
・準絶滅危惧種がまだ生息していてよかった。 ・都市化が進み、自然環境が減少している。 ・広大な公園ではあるが、種類が少ないのは環境保全ができていないのではないか。 |
調査の結果、意外にも貴重なカタツムリが浦添大公園に生息していることに喜ぶ一方、他地域と比較したときに生息種数が少ないことに驚いているようでした。
2-3 問題・課題
浦添大公園のカタツムリの生息環境について、団員が目指す課題としては、以下のような意見がありました。
|
・もっと種類が多い方が良い。 ・やんばるの環境に近づけたい。※ ・環境を複雑にする。(森、草原、水辺など) |
生物多様性を高めることを課題とした団員が多くいました。さらに、環境の多様性が種の多様性を生むことを理解されているようでした。
2-4 対策
上記の課題を実現するために、どうすれば良いかを団員で議論し、自由に対策を挙げてもらいました。
|
管理関連 ・生息地の除草、伐採等を避ける。 ・外来種のカタツムリは他に影響ない様、管理する。 ・カタツムリに優しい公園管理、草刈りの計画。 ・開発と自然保全のバランスを考えた公園管理を行う。
保全・環境創出関連 ・カタツムリの生息できる環境の保全。 ・自然環境を保全していくべき。(元々あった状態に近く) ・なるべく原生のままにしておく。 ・Let’s make more green areas. 緑地をもっと作りましょう。 ・人工に増やして散布する。絶滅危惧種とか。※ ・北部の環境に近づける取組みを行う。※
環境教育関連 ・カタツムリが小さな生物だったのでもっと身近に分かるよう、カタツムリの案内板を作る。 ・カタツムリ競争をさせる。 ・カタツムリに親しむ。今回の調査みたいな機会を増やす。
その他 ・浦添大公園に博物館と研究室を造る。 |
※これらのような自然環境の創出に関する対策は注意が必要です。本来存在していた環境を復元するのであれば問題は生じませんが、歴史的に生息・生育した記録がない動植物を新たに持ち込むことは、外来種問題を引き起こすことになります。

